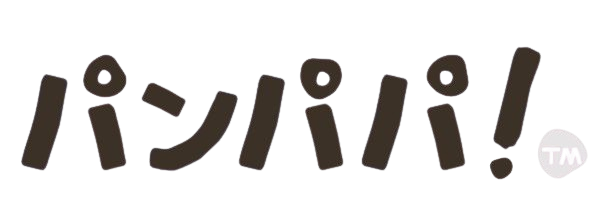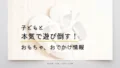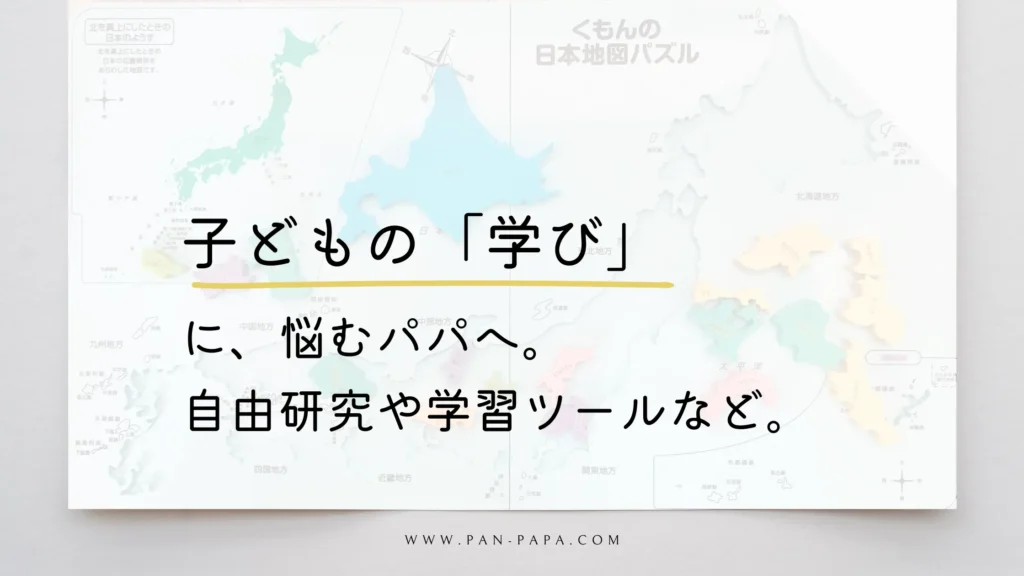
昨今は子ども教育に熱心なパパが増えてきたようです。私も自身に学が無い故、我が子の将来を思い「ある程度は」「最低限は」と思うところです。
勉強を教えてあげられる父であれたらいいのですが、悲しいかな私はそうではありません。
私にできることは、お子たちにとって最適な「学びの環境」と「学びのきっかけ」を作ること。子どもと一緒に「学び」と「向き合う」ことだけです。
同じように我が子の「学び」に悩むパンパパたちへ、自由研究や工作などの宿題や、学校や塾以外での貴重な体験やお手伝い、家でできるアプリやドリル、その他ツールなど、「きっかけ作り」やちょっとした「後押し」となりうる「アプローチ」についてまとめていきます。
Sub.1|通園/通学
長女が幼稚園年少の5月、妻が第三子の悪阻で身動きが取れなくなり、父親として日常の登園準備はできるようになりました。
しかし、「準備」ってそれだけではないんですね。年少の5月です。次から次へと「新しいもの」を用意する時期。明日は廃材を、次はビニール袋を、来週は雑巾を、しかも必ず記名を!
袋は三角に折ればいいのかな?雑巾に油性ペンで名前書いたら滲んだ!迷い、悩みは尽きません。これはやってみないとわかりません。
「ただの準備」と甘く見て、通園/通学の準備をママに全投げしていませんか?集めたり、揃えたり、準備したり。パパも一緒に向き合いましょう。
Sub.2|宿題
私はかつて宿題をやらない子でしたが、我が子には宿題をやるように言います。おかしな話です。
せめて一緒に向き合おうと努めてみてわかってきたのは、幼いうちの宿題は「大人ありき」だと言うこと。工作、自由研究などはもはや「大人への宿題」と言っても過言ではありません。
アイディアを捻出し、実際に子どもと一緒にそれをやり、最後にまとめる。硬くなった大人の頭ではこれがなかなか難しいんです。
同じような悩みをお持ちのパパたちへ、我が家で採用したサンプルを共有します。
Sub.3|体験/お手伝い
「体験格差」なる言葉を耳にする昨今、勉強だけでなく多くの体験をさせたいと願う親御さんが多いのではないでしょうか。
一緒にビスケットを焼く、料理の一部をやらせてみる、そんな「お手伝い」も立派な「体験」です。今すぐにでも始められます。
他にも、「おかあさんといっしょ」のスタジオ収録などの応募制の体験や、ららぽーとやイオンなどの商業施設で開催される無料イベントなどがあったりもします。長女は「プリンセスごっこプロジェクト」が大のお気に入りです。
子どもでも扱いやすい「お手伝いグッズ」や、思い出に残る「体験イベント」などをご紹介します。
Sub.4|英語学習/習い事
「英語教育は幼いうちに始めた方が良い」。耳にタコができるほどよく聞きます。
我が家でも、始めました。
まとめ
まずは父親として深い意味での「登園準備」をできるようにしておき、次に自由研究などの「大人が必要な宿題」を一緒になって取り組むことからはじめてみましょう。
並行して、家事のお手伝いなどの気軽にできる「体験」の機会を与えながら、英語学習や習い事などの実際の「学習」のステップへとアシストしていきたいところです。
とは言え、私も未だに「迷い迷い」です。
「こんなに幼いうちから?」「適切な熱量ってどのくらい?」「周りはもう始めてるのか…」
正直なところ、正解はわかりません。答え合わせができるのはまだまだずっと先。いえ、未来がどうであれ、それが親のせい、親のお陰とも言い切れません。お手上げです!
ただ一点、意識しておきたいのは、「後悔なきように」というところでしょうか。
子どもは本当に不思議な生き物で、好きなことは教えずとも勝手に学んでいきます。スポンジのように吸収します。まだまだ吸えるのにその機会が無い、逆に詰込み過ぎてただ溢れ落ちていくだけ。そんな状態だけは避けたいところです。
「学び」のジャンルもペースもタイミングも、人それぞれ、そのときどきです。子どもの興味や関心に注視しながら、適切なタイミングで、機会は損失しないよう、でも詰込み過ぎず、本人の意思やキャパを尊重した、飽くまで「アシスト」というポジショニングで上手に向き合っていきたいところです。
まずは、できるところから、探り探り。パパとして、パパなりに、参加してみましょう。