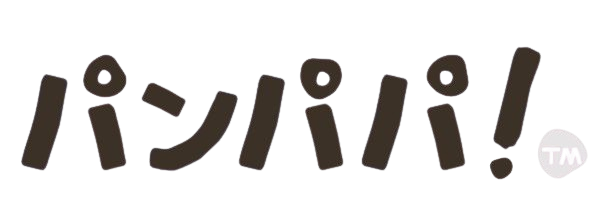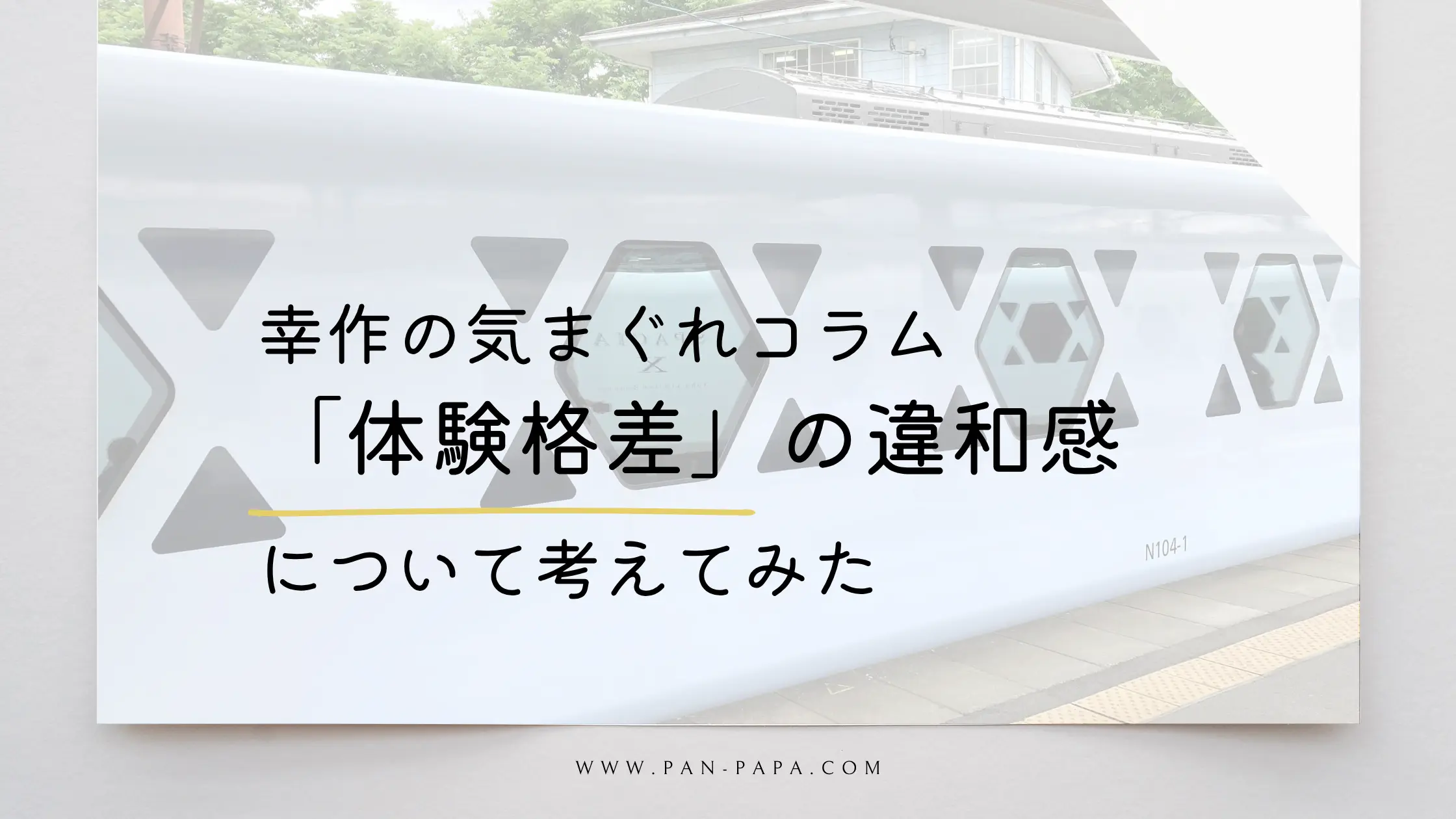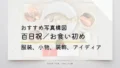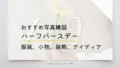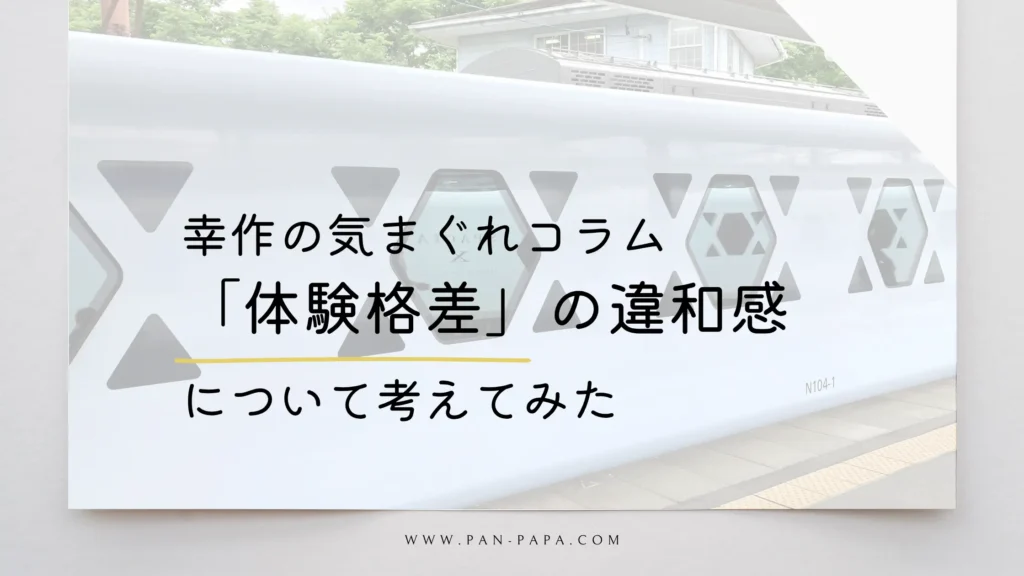
問題提起:「させてあげる」という感覚
「体験」というサブカテゴリーまで構えて記事を執筆し、さも「いろんな経験をさせてあげることが正義」みたいに語っているように見えるかもしれませんが、実はそれ自体にとても強い違和感を覚える今日この頃です。
「体験格差」なる言葉も耳にする昨今なので、どうしても「体験させたい」と願ってしまうのが親心。でも、果たしてそれが子どもにとって本当に「体験したいこと」なのか、「いい体験」なのか、それは親が決めることでも知ることでもない、と思う次第です。
こんなことを言っては元も子もないのですが、子どもはそもそも生まれたその瞬間から「彼」の人生を生きているわけであって、確かに生物学的には「我が子」ですが、人間的には全くの別人格の「誰か」なんですよね。
「させてあげたい」というあたかも「豊かさ」のように見えるアプローチも、実はむしろ窮屈にさせているような、何かを無理強いしているような、むしろ「人権問題」にすらなりかねないような危うさすら秘めているように思います。
言葉を選ばなければ「押し付けんな」と思っているかもしれないわけです。
子どもにとっては些細なことも立派な体験
我が家では「週末をずっと家でゆっくり過ごすのがむしろしんどい」という完全な親事情から、ほぼ必ずおでかけをします。
とはいえ、お金には限りがありますし、我が家は行き過ぎた倹約家でもあるため、旅行のようなビッグイベントを毎週しているわけではありません。思い描くような「体験」を思うようには経験させてあげられません。
日ごろから提供できるおでかけは、近くのららぽーと、少し離れたイオン、たまに祖父母の家とか、たまに動物園とか、せいぜいそんなもんです。
そしてどうにも良いプランが思い浮かばない時は、徒歩圏内の公園に連れて行ったり、近くの踏切で電車を見たり、そんな他愛もない過ごし方をしています。
ただ、時々思うんです。
公園で初めて知り合った同世代の子とひょんなことから仲良くなって追いかけ回しているときの娘の表情、たまたま上りと下りの急行電車がハイスピードですれ違う瞬間を踏切前で目撃できたときの息子の目、それはお金と時間をかけて策略したどんなパーフェクトプランを「させてあげている」ときよりも、圧倒的にキラキラ、ギラギラしているんです。
「そんなことで?」と思うこともありますが、子どもにとってそれは何にも代え難い究極の「体験」なんだと思います。
親側から意図して提供した体験ではありません。偶然そこで自然発生した体験です。しかし、お子たちにとっては間違いなく意味のある尊い体験なわけです。
親だって人格を待った一個人
自然発生的な体験が尊いものであるとわかってはいるものの、毎週末近くの公園か踏切でやり過ごすだけでいいかと言うとそうではありません。というか、そうしたくはありません。
その理由の一つは、もっと他にもあるかもしれない尊い体験の機会を失わせてしまっているのではないか、という「親心」。
もう一つの理由は、コレが最も重要な理由になりますが、ただただシンプルにそれじゃ親がつまんない、という「親の勝手」です。
いや、もはやどちらも「親の勝手」なのですが、どうしても、「これでいいの?」という疑念を拭いきれないわけです。なんとなく、「それでよさそう」な雰囲気が子どもたちにはあるにも関わらず、です。
そうです。親も人です。つまらんもんはつまらん。それはどうしようもありません。いつもと違うこともしたい。仕方ありません。
もちろん、子どもが電車好きなら、一緒に電車好きになるのが理想ではあります。毎週末いろんな電車を見るだけの旅でも最高の体験になるでしょう。私の姉も親になって電車好きになりました。尊敬します。
でもそれはある程度、親側にも素質があってのことなのではないかとも思います。好きになれる素質があったんです、きっと。
例えば、私も息子にプラレールやトミカを買ってあげる中で、割と好きになってきたところはあります。素質はあったのでしょう。中古屋さんで見つけた古い廃盤トミカに一目惚れをして「買ってあげるよ」とドヤ顔で買って”あげる”こともあります。
ただ、プリンセス好きの娘とプリンセスごっこをするのはとてもとても難しい。男なんだから姫じゃないし、男だからって王子役を本気でやれるかって言われるとそうじゃない。オラフすらしんどい。スヴェンでギリです。
そんなもんでしょう。もちろん本気でプリンセスごっこをしてあげる、まるで王子様のような最高のパパが存在することも知っています。賞賛しかありません。
それでもやっぱり、無理なもんは無理。親は親でも、私は私。そこは拭いきれません。
親として我が子が好きなものを好きになれるのが理想ですが、無理なものは無理なままで無理しなくてもいいのではないかと思います。「否定」さえしなければ、です。
それぞれの、やりたい体験
親も子も、別人格の個人です。それぞれにそれぞれの好き嫌い、そして、やりたいことがある。それは忘れてはいけない大前提です。
私は第三子が生まれた瞬間から、「この5人家族で47都道府県を制覇する」という夢を掲げました。
当時長女は4歳。仮に一緒に旅行に行ってくれるのが15歳くらいまでだとして、残り約10年で全国制覇するには年4回の旅行が必要です。日々の生活は死ぬほど節約し、ひたむきに着々とミッションを遂行しています。
でも、知っています。子どもたちは沖縄の綺麗な海より近所の市民プールの方が好きかもしれない。温泉なんかより、ママと入る毎日のお風呂の方が楽しいのかもしれない。私にとってのプリンセスごっこばりに、子どもたちにとっての旅行はむしろ難儀なことなのかもしれない。
じゃあ、やめる?
いいえ、やめません。
だって、私が、パパが、やりたいんだもん!君たちが付き合ってくれるうちに、いろんなところに行きたいんだもん!パパだってどうにかスヴェン役くらいは付き合ってあげてるもん!です。
それではダメなのでしょうか。「親事情で子を振り回す親」と認定されてしまうのでしょうか。じゃあ「日本中のあらゆるいいところを幼い頃から見せてあげたい」とでも言えばいいのでしょうか?
「親のしたいこと」を、「子どもにさせてあげたいこと」にすり替えればいいのでしょうか。
ああ、人権侵害です。押し付けです。
予期せぬ「いい体験」
少し話を戻しますが、徒歩圏内の公園でも、最寄りの踏切でも、自然発生的な「いい体験」が降ってくることもあるわけです。親が意図的に「提供」して「あげる」ことなく、生まれうるんです。
逆もしかりです。我が子の「好き」に付き合う中で、私もトミカを好きになり、中古のトミカにときめくことだってあるんです。
偶然の産物ですね。まだ経験値の低い子どもたちにとっては、そんな偶然がそこら中に転がっています。
先日、47都道府県制覇の一環として日帰りで日光に赴きました。メインは東照宮。子どもたちがときめくような観光スポットではありません。もちろん、子どもたちが希望した体験でもありません。
関東では数少ない世界文化遺産を幼いうちに見せてあげたい?いえ、47都道府県制覇の証明としてその県の象徴の前で写真が撮りたいだけです。親の勝手、親の夢に付き合わせただけです。
繰り返しになりますが我が家は行き過ぎた倹約家で、しかも年4回ペースで旅行をしたい故、時間が許せば交通ルートは「最安」を選択します。
ただ、今回は日帰りということもあり、時間の都合から帰路は特急を選択しました。「スペーシアX」です。※もちろん電車好きの息子が喜ぶ可能性は考えていました。
結果、疲れ果てているはずの帰り道にも関わらず第二子息子は大興奮。電車に興味のない第一子長女ですら「この電車はカッコいい!」と言い、駅に止まる度に発車までの数秒だけ下車して車体を見ていました。
これもまた、偶然の産物です。まさか、娘まで楽しめるとは。娘のためを思って意図的に提供させてあげる体験では見つけることのできなかった副産物です。
やはり、「いい体験」はそこら中に転がっているんです。親の勝手、親事情のイベントの中にだって隠れているんです。
「副産物」による「副産物」
以後、息子だけのおもちゃだったはずの「プラレール」で、娘も一緒になって遊ぶようになりました。
息子はやはりレールの上を走る車体そのものが好きなようですが、娘は陸橋やトンネルなどの景観をデコる方で楽しんでいます。
元々シルバニアファミリーが好きな娘です。好きな世界観を作る、おままごと的な玩具としてプラレールを使い始めました。おでかけごっこ、旅行ごっこみたいなやつです。
当時2歳の息子はまだレールを繋ぐのが上手ではないため、これまでは親が敷いたレールの上(悪意のある表現)を走らせていました。
しかし、当時4歳の娘はその気になればそこそこのコースを作れます。おかげさまで、親の介入なく、子ども二人でもある程度の遊びが成立するようになりました。これが親としてどれだけ助かることか…
娘のためにいい体験を提供してあげたいと思ったら、栃木の東照宮ではなく隣県の茨城のシルバニアパークに行けばいいんです。間違いなく喜んでくれます。シルバニアをもっと好きになれたかもしれません。
しかし、親の勝手で栃木の東照宮に付き合わせた中にたまたま娘にとっても楽しい体験が転がっていたんです。そして、プラレールをシルバニア的に遊ぶことを覚えたんです。
世界が広がったんです。新たな価値観が生まれたんです!そんな偶然があるんです。
偶然得た体験こそ広い
「させてあげたい」と思ってさせる体験は、必然的に子どもの関心やレベルに合ったものになりがちです。
シルバニア好きの子をシルバニアパークに連れて行く計画は立てられますが、東照宮に連れて行ってプラレールを好きになってもらう計画を立てるのは到底無理な話です。風が吹いて、桶屋が儲かった、結果論として言えることであって、それを事前に予期して誘導するのはさすがに難しい。
そう考えると、意図的にさせてあげられる体験には限界があります。逆に、偶然降ってくる、偶然落ちている体験は無限です。
娘はさらなる偶然を拾いました。東照宮からの帰り道、自宅の最寄駅に着いた時に言いました。「なんか、帰りの方が早かったね」と。
そうそう、それに気づかせるために往路は特急を使わなかったんだ?いえ、安いからです。むしろ復路で特急に乗ったのは、プラン的に時間がないから、致し方なく、です。
しかし、それが4歳の娘に気付きを与えたんです。特急ってのは、早いんだ、と。
「なんで?」
「こまめに止まらないから。」
「なんで?」
「あんまり休まず走り続けるから。」
「か、かっこいいー!!!」
何でもかんでも親の義務、使命ではない
「いろんなことをさせてあげたい」という気持ちは否定しません。いろんなものを見て、いろんなことをして、世界を広げてほしい。親として心底そう思います。
意図的に提供する体験がその年齢に適した体験であることもとても良い利点です。私も無理のない範囲で続けていきます。
問題提起しておいてこんな回収は反則ですが、やはり「可能な限りいろんな体験をさせてあげたい」という考えは持ち続けた方が良いようにも思います。
ただ、それを「義務」のよう捉えてしまうのは危険かもしれない、という話です。
「これを見ておいた方がいい」「これはやっておくべき」というアプローチになると、子どもたちはまるで「宿題」と向き合っているような気持ちになるでしょう。
親が「体験格差是正」という使命に躍起になってしまうと、お子たちもその体験を「義務」と感じ、つまらなくなってしまうリスクが伴う気がします。
しかもそれが子ども用に設けた体験で、親としてはクソほどつまんない体験だった場合、誰も得をしないんです。もう、近くの公園か踏切でよかったとすら。
つまり、「体験格差是正」までも親の義務と捉える必要はないのではないか、と思います。
さらに、自我を殺してまで子どもたちの興味や関心のあるものだけに触れさせる必要もありません。体験範囲が狭くなってしまうだけです。
親も子も、人。自由でいいのではないでしょうか。みんな、自由でいいんです。自由に行きましょう!生きましょう!
家族みんなで楽しく暮らしてさえいれば。
多くの体験をさせてあげる目的は「世界を広げる」ということにあるはずです。それなら、まずは「体験をさせてあげなければ」という狭い考えから少しだけ脱却してみるところから始めてみませんか?
「パパはみんなでこれを見に行きたい」「ママはあそこに行ってみたい」、そんな親事情に付き合わせる中にもきっと予想外で予想以上の刺激がたくさん散らばっています。
むしろ、親がやりたい親レベルで刺激的な体験は子どもにとっても刺激的に決まってます。仮にハイレベルすぎて退屈に感じても、それはそれです。
パパはなんでこれが見たかったんだろうと考えたり、ママはこれのためにここに来たかったんだなと推測したり、そんな想像力を働かせる体験も良いでしょう。
寄り道という自由、遠回りという無駄、効率という工夫、その中にある楽しさ、いろんな気づきも得られるかもしれません。そのときはわからなくても、いつか振り返ったときに気付いたっていいです。
子どもたちは楽しむ天才、遊ぶ天才です。同時に、学ぶ天才でもあります。何をしてたって、何かに気づき、拾い上げ、吸収してくれます。
それが子どもです。それら全てが子どもにとっては素晴らしい体験です。
「体験」は、あげなくてもいいんです。どこにでも、そこに、あるんです。何かをしていれば、どこかに行ければ。そう!家族みんなで、楽しく、仲良く、暮らしてさえいれば。
「今日は何したい?」「鉄道博物館行きたい。」「この前も行ったじゃん」「でも行きたい」「うーん、行こう!」
それでいいんです。
「今度は四国行こう!」「どこそれ、遠い?」「うん、かなり」「えー、楽しいの?」「わかんないけど、パパの夢なんだ、ごめん。」「うーん、いいよー」
そんなもんです。
我が家はこれからもそうやって、ただただみんなで楽しく生きていこうと思います。
楽しく暮らす中に、たまたま、良い体験が転がっていることを祈りながら。
2025.07.01
幸作
追記
書いていて気づきました。このコラムは「私(パパ)も私らしくいていい」という必死の正当化ですね。ああ、押し付けです…
おまけ
当コラムのスタンスよりももっとひどい、9割が愚痴を締める育児記録はこちら。
「ママとパパの共倒れだけは回避!」「目指すは100点ではなく72点くらいの育児!」がモットーです。息抜きがてら、是非。